
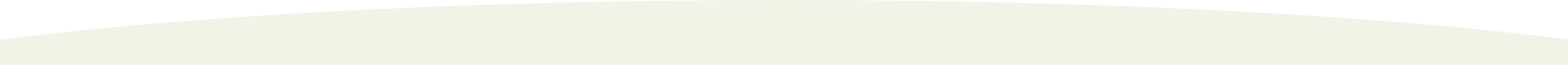


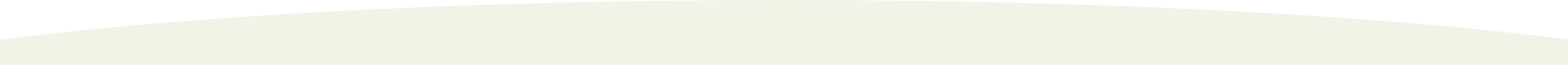

2025.07.23 掲載
茨城県からは15枚の応募があったよ。その中から3枚をご紹介。
久松師範よろしくお願いします!
水戸市「逆川こどもエコクラブ」
トカナ新聞を書いてくれたみなさんへ
師範から一言!
トカゲとカナヘビについて、親子で一生懸命調べたり絵をかいたりして、壁新聞を作成する様子が目に浮かびました。
普段よく見かけることができるトカゲとカナヘビでしたが、別の場所ではあまり見られないことに気づきました。すばらしい発見だと思います。研究の第一歩は、比べることだと思います。将来、もしかすると自然研究者になるかもしれません。その第一歩が、今回の発見になるかもしれませんね。
生きものの絵も、とてもよく描けています。トンボの翅の大きさ、甲虫の脚先の爪の様子など、細かい点も、注意深く観察しています。
壁新聞などにまとめると、活動を振り返ることができるので、体験したことが確実に定着すると思います。壁新聞づくりなどの振り返りを大切にして、活動を続けていってください。
とっておきのゴシドウ★
まだ、小さいお子様のようですから、壁新聞にまとめるのにも、保護者の方の手助けがたくさんあったのではないか?と推測いたします。難しいながらも、絵を描いたり、絶滅という言葉を学んだりしていった経験は、貴重な体験だったと思います。一緒に、作品を仕上げることができたことが、大切なことだと信じます。
ところで、トカゲとカナヘビは同じ爬虫類ですが、やはり姿に違いがあります。それらの区別がつくように、この点でも比べてみていってください。観察の目が、養われていくと思います。
小さいころの体験は、少なからず将来に影響していくでしょう。体験を重視しながら、今しかできないことを、たくさんしてほしいと思いました。未来に研究者が育つことを期待しています。
ヒヌマイトトンボと涸沼大自然を書いてくれたみなさんへ
師範から一言!
涸沼にどんな生き物がいるのか、一目でわかる新聞を作成してくれました。涸沼の観察会で、そこの自然の豊かさを感じ取った気持ちが、とても感じられました。
涸沼でまず思い出すのは、新聞でも紹介してくれたラムサール条約の登録湿地であることですね。人とのかかわりの中で、大切にされていることが、新聞でも確認できました。それから、ヒヌマイトトンボの発見地であることも知っておいてほしいことです。このトンボは、1971年に涸沼で廣瀬誠さんと小菅次男さんによって発見されました。涸沼のような汽水域のヨシ原に生息する珍しい種で、現在は絶滅危惧種に指定されています。機会があったら、ぜひ保護活動にも参加してください。
解説が長くなってしまいましたが、涸沼の切り絵の上に、生息する生きものの写真を貼りつけたのも、工夫のひとつですね。生きものの発生時期や種数も調べ、図にして分かりやすく紹介してくれました。
涸沼の自然が良くわかる新聞にまとめることができました。
とっておきのゴシドウ★
新聞をみて、涸沼にどんな生き物が生息するのかを知ることができました。
さて、同じ紙面ですが、さらに情報を盛り込んでみましょう。例えば、涸沼の切り絵の上に確認できる生きものの写真を貼りましたが、どこに多く生息しているかの位置情報を加えたりすると、どう見えるでしょうか?水鳥が良く見られる場所や、昆虫の生息する場所が分かると、より中身の濃い新聞が完成します。調べる中で、感じ取ったことなども加えると、気持ちも伝わります。バージョンアップした涸沼の生きもの地図の作成を期待してしまいます。
身近にある自然を、これからも調べていってください。
もやせばごみわければ資源 ヤバいぞ日本!!へらそう燃やせるゴミを書いてくれたみなさんへ
師範から一言!
内容ごとに小見出しをつけたり色分けしたりしてあるので、見やすさに配慮されていることが分かります。ゴミの問題について、とても分かりやすく壁新聞にまとめることができました。
内容を詳しく見ると、世界のゴミ事情を調べることからはじまり、水戸市への取材、自分で取り組んだこと、そして最後にまとめを記してくれました。調査の過程が分かるのはもちろんなのですが、自分たちが直に聞いたり行ったりしたことが、きちんと記録されており感心しました。また、調べて得られた情報を図や表にまとめることも行い、視覚的な効果も高めることができたと思います。ときおり写真を貼ってくれたので、活動の様子を知ることもできました。
かつて私たちは生活の中で出たゴミを肥料として活用したり、そもそもゴミが出ないような生活スタイルを実践したりした時代がありました。その頃に戻ることはできませんが、何らかのヒントが隠されているかもしれません。いろいろな面から、ゴミについて考えていきたいですね。
とっておきのゴシドウ★
繰り返しになりますが、調査の過程が分かるように紙面が構成されていたので、ゴミについて見識を深めていった様子がよく分かりました。さらに、新聞感を出す方法として、見出しに、訴えたいことを記す方法があります。国別のゴミの処理割合のグラフに「ゴミ焼却の割合高い日本」というようなタイトルをつけると、その内容に注目が集まります。ちょっとしたことですが、自分の伝えたいことが、より鮮明になるでしょう。参考にしてみてください。
久松師範、ありがとうございました!次回はどこの地域かな?お楽しみに!

ご意見ご感想もお待ちしております!
〒101-0032 東京都千代田区岩本町1丁目10-5 TMMビル5F
公益財団法人 日本環境協会
TEL:03-5829-6359 FAX:03-5829-6190
Email: j-ecoclub@jeas.or.jp
2024年の壁新聞道場一覧はこちら https://www.j-ecoclub.jp/kabe/202412272024.html
2023年の壁新聞道場一覧はこちら https://www.j-ecoclub.jp/kabe/202403312023.html
2022年の壁新聞道場一覧はこちら https://www.j-ecoclub.jp/kabe/202303310000.html