
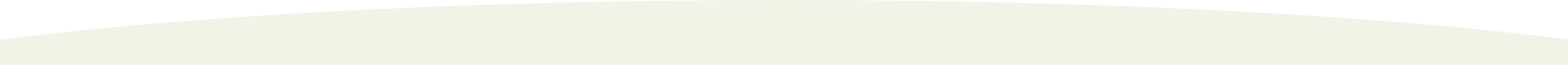


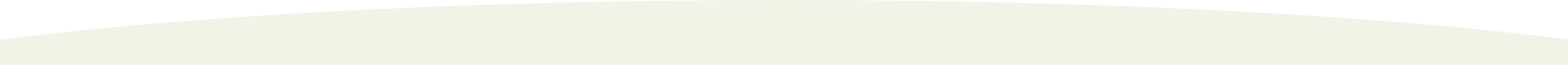

2025.10.22 掲載
滋賀県からは12枚の壁新聞の応募があったよ。
今週は2枚の壁新聞をご紹介。池田師範よろしくお願いします!
山内エコクラブのみなさんへ
師範から一言!
新聞をみると「川をきれいにするか汚くするかは私たちの行動しだいです」というメッセージが飛び込んできて、どのようなことが書いてあるか興味がひかれます。地図に記してくれた活動場所をみると野洲川のかなり上流のようですね。
黒滝トレッキングで、"川の音を聞くとリラックスできます"とありますが、まさにそうですよね。今年山にいったときに、私も同じように川の音を心地よく感じました。黒滝をインターネットで検索したら自然豊かな林道や川原の写真がいっぱい見つかりました。多様な生き物が生息していそうです。カエルやカニが見つかって楽しいトレッキングになりましたね。写真の手のひらにのった小さなカエルは何ガエルでしょう?
天ヶ瀬ダムの浮遊ゴミが年に100万トンもあるとはびっくりしました。目に見える大きなゴミの多さに驚くばかりですが、一方で目に見えないマイクロプラスチックが野洲川の砂に入っているということにも驚いたことでしょう。けんびきょうでないと見えないくらいに細かくなってしまったプラスチックは浮遊ゴミのようには回収できないですね。普通のプラスチックが分解されるのに400年以上かかりますが、近年は微生物によって分解することができる生分解性プラスチックというものが使われ始めてきています。それでも生ゴミのようにすぐに分解されるわけではなく、中には数ヶ月から数年かかるものもあるようです。プラスチックの製品は今では身の回りのいたるところにありますので、「私たちにできること」に書いてくれたことに一人一人が取り組んでいってください。
とっておきのゴシドウ★
野洲川上流にはいつもアカハライモリがいるというのは、イモリにとって生息するのによい環境がたもたれているということですね。アカハライモリは環境省のレッドリストで準絶滅危惧種になっていて、見かける機会がへっていると感じています。カワムツは滋賀県には元々生息していたようですが、関東では近年見かけるようになった国内外来種です。国内外来種というのは、外国から来たわけではありませんが、その地域に昔はいなかったのに人やモノの移動にともなって持ち込まれて定着してしまった種類のことです。北海道でのアズマヒキガエルが有名ですが、昆虫では沖縄に生息するリュウキュウツヤハナムグリが近年は都内各所の公園でみかけるようになってきています。その地域の生態系のつながりがこわれてしまうこともあり、国内であっても移動しないように気をつけることが大切です。
日野川エコスクールのみなさんへ
師範から一言!
新聞の真ん中に上から下まで日野川のイラストがかいてあって遠くからでも目をひくデザインですね。年10回のエコスクール活動がとても充実した内容であることが新聞から伝わってきます。
漂流ゴミの写真をみるとかなり大きなゴミが山づみされていてびっくりしました。川の流れに運ばれて漂流したゴミがこれだけあるとなると、流れに運ばれずに川底にたまったゴミもたくさんありそうです。ゴミのほとんどがペットボトルとビニール袋ということなので、琵琶湖の生き物への悪影響が現れるまえに、プラスチックゴミ問題をみんなで考えていきましょう。
川の診断を5つの指標を用いてレーダーチャートのグラフにあらわしてくれて、上流、中流、下流のちがいがとてもよく分かります。上流から下流にむかって指標が悪くなっているので、考えてくれた対策をぜひためしてみてください。日野川、出雲川の水質の評価において、計測したCODの数値を地図上に(青)(黄)(赤)でマークしてれたまとめ方は、分かりやすいと思いました。日野川は下流にむかうほど有機物が大きくなっていることが分かります。出雲川は田の排水が影響しているということを考えてくれました。GoogleMapで出雲川をみてみると、確かに出雲川をはさむように周り中に田んぼがありました。CODの大きさの原因を分析して考えるというのはすばらしいプロセスだと思います。
"川はだれのもの?"という歌を初めて知って、よい歌詞なのでYouTubeで探して聴いてみました。いい歌ですね。「日野川のふしぎまとめ」に10項目のまとめをみると、"農業用水""護岸"といった人の生活にかかわる言葉が出てきますので、人の生活をどのようにしていくのがいいのか考えながら、みんなの川を豊かにするために「たんけん・はっけん・ほっとけん」の活動をぜひ続けていってください。
とっておきのゴシドウ★
川の診断の5つの指標の中に「地域とのつながり」があり、対策を考える上で役立つ指標だと感じました。田んぼの排水やゴミの有無が"地域とのつながり"の評価に関わると思いますが、川で遊べる場をつくるという対策は親水だけでなく、地域とのつながりにも関わってきそうですね。対策の内容によって2つ以上の指標に影響することもあると思うのでぜひみなさんでPDCAサイクル(計画→実行→評価→改善)をまわしていってください。
ところで"ゆたかな生きもの"は生物多様性の項目だと思いますが、生物多様性の危機の中に「外来種の侵入」や「地球環境の変化(温暖化など)」があげられています。日野川での外来種や水温の変化なども調査して分かりましたらぜひ教えてください。
池田師範、ありがとうございました!次回はどこの地域かな?お楽しみに!
ご意見ご感想もお待ちしております!
〒101-0032 東京都千代田区岩本町1丁目10-5 TMMビル5F
公益財団法人 日本環境協会
TEL:03-5829-6359 FAX:03-5829-6190
Email: j-ecoclub@jeas.or.jp
2024年の壁新聞道場一覧はこちら https://www.j-ecoclub.jp/kabe/202412272024.html
2023年の壁新聞道場一覧はこちら https://www.j-ecoclub.jp/kabe/202403312023.html
2022年の壁新聞道場一覧はこちら https://www.j-ecoclub.jp/kabe/202303310000.html