
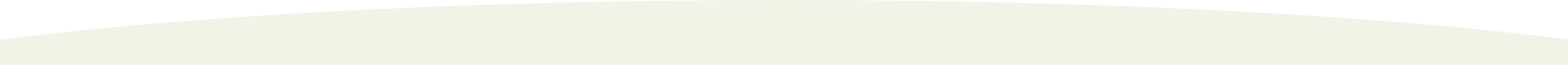


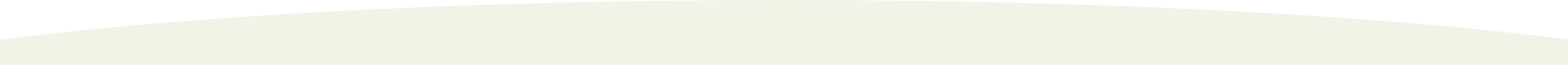

2025.11.05 掲載
 大阪府では、大阪府を中心に地域に根差した環境活動を実践している子どもたちが、それぞれの環境活動の紹介を通じて、相互の交流を深めることで、お互いの活動を「知る」「たたえる」「交流する」ことを目的として、「大阪ATCこどもエコクラブ交流会」を毎年開催しています。(主催:大阪府、大阪市、おおさかATCグリーンエコプラザ)
大阪府では、大阪府を中心に地域に根差した環境活動を実践している子どもたちが、それぞれの環境活動の紹介を通じて、相互の交流を深めることで、お互いの活動を「知る」「たたえる」「交流する」ことを目的として、「大阪ATCこどもエコクラブ交流会」を毎年開催しています。(主催:大阪府、大阪市、おおさかATCグリーンエコプラザ)
このたび、大阪府より10月26日(日)に開催された「令和7年度大阪ATCこどもエコクラブ交流会」のレポートが届きました★
当日の盛り上がった様子をご紹介します^^
近畿地域で元気に活動している6クラブが参加してくれました!
・SDGs学ぶ隊(兵庫県神戸市)
・NOSG(大阪府高槻市)
・ガールスカウト大阪府第21団(大阪府吹田市)
・高槻市立第6中学校・自然観察同好会(大阪府高槻市)
・せいわエコクラブ(大阪府大阪市)
・地球☆プロテクト とあるた(大阪府大阪市)
1.活動報告発表
各参加団体の活動をまとめた壁新聞等を展示し、参加団体が1団体ずつ順に参加者に向けて日々の活動について元気に発表してくれました!
 【せいわエコクラブ(大阪府大阪市)】
【せいわエコクラブ(大阪府大阪市)】
「大阪の水」を知りたいという思いから、近畿の水瓶である琵琶湖について学び、琵琶湖での活動について壁新聞にして発表しました。
 【SDGs学ぶ隊(兵庫県神戸市)】
【SDGs学ぶ隊(兵庫県神戸市)】
竹林が増えすぎると危険ということを知り、竹チップをつかって植物や野菜などを育て、竹チップが有効に活用できることについて、壁新聞にして発表しました。
 【ガールスカウト大阪府第21団(大阪府吹田市)】
【ガールスカウト大阪府第21団(大阪府吹田市)】
普段から清掃活動をしている細川と滋賀県にある石田川の生態系や水質調査を実施し、2つの川の違いについて壁新聞にして発表しました。
 【高槻市立第6中学校・自然観察同好会(大阪府高槻市)】
【高槻市立第6中学校・自然観察同好会(大阪府高槻市)】
桂川河道内竹林の伐採活動に参加し、伐採した竹をチップに加工したものを竹林内に敷き、遊歩道づくりを行ったことなど、動画にして発表しました。
 【NOSG(大阪府高槻市)】
【NOSG(大阪府高槻市)】
桂川大山崎地区で特定外来種の除去活動や、鵜殿のヨシ原の保全活動で、つる草ぬき作業などに参加したことをPowerPointにして発表しました。
2.交流パート
 つぎはお楽しみの交流!会場内に各参加団体の活動をまとめた壁新聞等を展示し、参加団体は「説明組」「取材組」に分かれて15分交代で説明・取材を行いました。
つぎはお楽しみの交流!会場内に各参加団体の活動をまとめた壁新聞等を展示し、参加団体は「説明組」「取材組」に分かれて15分交代で説明・取材を行いました。
全体発表を聞き、気になっていたことについて、子どもたちが中心となって取材をしました。取材した内容を共有して、これからの環境活動をどのように展開するべきかを考えるいい機会になったようです☆
みんな、熱心ですね~!
3.壁新聞づくり講座
 そしていよいよ今回の目玉企画!こどもエコクラブ壁新聞道場の西澤浩美師範が講師をしてくださり、壁新聞の作り方について学びました。今年のエコ活コンクールに向けて、壁新聞づくりの参考になったと思います。どんな力作がつくられるのか、とても楽しみにしています^^
そしていよいよ今回の目玉企画!こどもエコクラブ壁新聞道場の西澤浩美師範が講師をしてくださり、壁新聞の作り方について学びました。今年のエコ活コンクールに向けて、壁新聞づくりの参考になったと思います。どんな力作がつくられるのか、とても楽しみにしています^^
4.おおさかATCグリーンエコプラザ見学ツアー
 そのあとは、会場であるおおさかATCグリーンエコプラザの見学ツアーに出発!たくさんの企業が環境に関係する取組をしていることを学びました。
そのあとは、会場であるおおさかATCグリーンエコプラザの見学ツアーに出発!たくさんの企業が環境に関係する取組をしていることを学びました。
5.感想発表
最後はみんなで今日の感想を発表・共有する時間です。
交流会に参加したことで、他のクラブの発表を聞いたり、企業の環境への取組の説明を受けたりなど、たくさん学んだことを発表てくれました!他のクラブと一緒に活動してみたいといった感想もあり、各クラブにおける今後の交流のきっかけになりました。来年またみんなに会うのが楽しみですね!
![]() ~全国事務局より~
~全国事務局より~
今回で11回目を迎えた大阪ATCこどもエコクラブ交流会。「地域の子どもたちが学び合い、つながる場をつくりたい」という想いから始まったこの会は、大阪府さん・大阪市さん・ATCさんのご協力のもと、近畿一円の仲間たちが集い、年々その絆と交流の輪を深めています。
企画・準備から当日の運営まで、地域のクラブを応援する皆さんが力を合わせてつくり上げるこの会は、まさに「地域のクラブを地域の大人が支える」こどもエコクラブの理想的なかたちです。
地域の中で、地域の仲間とともに育つエコの輪。今年もたくさんの笑顔と出会い、気づきと発見が生まれました。大阪府内はもちろん、近畿各地からも参加を楽しみにするクラブが増えています。
今回参加できなかったクラブの皆さんも、ぜひ来年は参加して「地域だからこそ生まれるつながりと発見」を感じてください◎主催・運営のみなさま、ありがとうございました!