
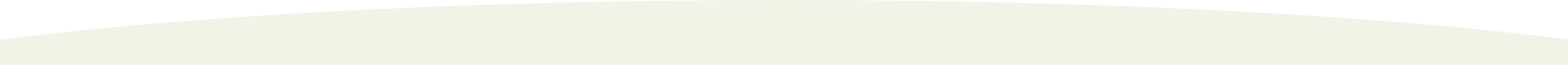
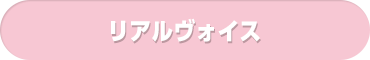

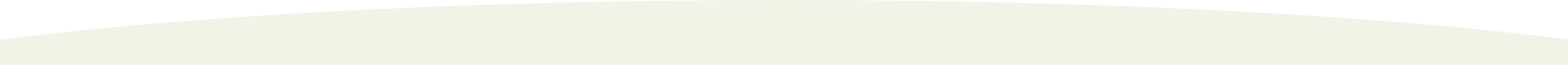
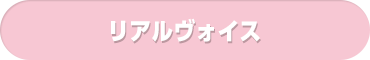
2020.05.10 掲載
今回は島根県松江市の「忌部(いんべ)わくわくサファリ」さんにお話をうかがいました。
島根県の東部、宍道(しんじ)湖と中海に挟まれた地域に広がる松江市は、山陰地方最大の都市です。「水の都」として有名ですが、天守閣が国宝に指定されている松江城のほか、由緒正しい神社が数多く存在する歴史の街でもありますね。
忌部わくわくサファリさんは、そんな松江の豊かな自然の不思議に気づくことを目的に川の生き物調べなどを長く続けてきており、2018年には環境省の「こどもホタレンジャー」ではみごと奨励賞を受賞されています。
それでは、インタビュー開始!![]()
 活動を始めたきっかけは何ですか?
活動を始めたきっかけは何ですか? 私たちが暮らしている松江は、とても自然に恵まれた環境ですが、それを実感していない子どもたちが多いように思いました。そこで、「この“松江”の環境のすばらしさに気づいてほしい」、「自分で思う存分体験してほしい」、そして「将来この松江に帰って来たいと思える大人になってほしい」という思いから、2005年にこどもエコクラブ「忌部わくわくサファリ」の活動を始めました。
私たちが暮らしている松江は、とても自然に恵まれた環境ですが、それを実感していない子どもたちが多いように思いました。そこで、「この“松江”の環境のすばらしさに気づいてほしい」、「自分で思う存分体験してほしい」、そして「将来この松江に帰って来たいと思える大人になってほしい」という思いから、2005年にこどもエコクラブ「忌部わくわくサファリ」の活動を始めました。 クラブの「自慢」を教えてください。
クラブの「自慢」を教えてください。 近くにある千本ダム周辺をはじめとする森や川での生き物調査を中心に行っています。子どもだけでなく大人も一緒に自然体験ができるのが特徴で、参加者みんなが楽しむことができる活動です。むしろ、大人の方が夢中になることもあります(^^)!
近くにある千本ダム周辺をはじめとする森や川での生き物調査を中心に行っています。子どもだけでなく大人も一緒に自然体験ができるのが特徴で、参加者みんなが楽しむことができる活動です。むしろ、大人の方が夢中になることもあります(^^)! これまでの活動で一番印象に残っているものは何ですか?
これまでの活動で一番印象に残っているものは何ですか? 宍道湖のシンボルである「シジミのふしぎ」を学習院女子大学の品川明教授から学んだことです。子どもたちはまずシジミを観察し、水管が出たり、足が出たりするその動きに驚き、最初は食べものの一つでしかなかったシジミが、生き物であるということを実感しました。観察した後には、一番おいしい食べ方を学び(砂抜きや、ねかせることでじっくり旨みを引き出す方法)、おいしくいただきました。また、シジミについて知りたいことを子どもたちから聞きだし、その調べ方のヒントをもらったりして、シジミについて詳しくなることができました。
宍道湖のシンボルである「シジミのふしぎ」を学習院女子大学の品川明教授から学んだことです。子どもたちはまずシジミを観察し、水管が出たり、足が出たりするその動きに驚き、最初は食べものの一つでしかなかったシジミが、生き物であるということを実感しました。観察した後には、一番おいしい食べ方を学び(砂抜きや、ねかせることでじっくり旨みを引き出す方法)、おいしくいただきました。また、シジミについて知りたいことを子どもたちから聞きだし、その調べ方のヒントをもらったりして、シジミについて詳しくなることができました。 15年以上の長きにわたり活動を続けていらっしゃいます。長く続けていてよかった!と思うことを教えてください。
15年以上の長きにわたり活動を続けていらっしゃいます。長く続けていてよかった!と思うことを教えてください。 小1で登録した子が6年生まで続けてくれるのが嬉しいです。子どもたちの環境への気づき等、成長を感じますね。地域の自然を少しずつ見つけていく活動ですので、その不思議には限りがないなと感じています。子どもたちと一緒に体験していることは、まだ序章ですね。
小1で登録した子が6年生まで続けてくれるのが嬉しいです。子どもたちの環境への気づき等、成長を感じますね。地域の自然を少しずつ見つけていく活動ですので、その不思議には限りがないなと感じています。子どもたちと一緒に体験していることは、まだ序章ですね。 逆に、長くやっているからこその悩みや、困りごとはありますか。
逆に、長くやっているからこその悩みや、困りごとはありますか。 企画を考えてくれるスタッフの育成ですね。島根大学教育学部の学生が基礎体験活動として、関わってくれるようになり、助かっています。
企画を考えてくれるスタッフの育成ですね。島根大学教育学部の学生が基礎体験活動として、関わってくれるようになり、助かっています。 活動を始めた当時の子どもさんと今の子どもさんで、活動しているときの様子や性格・気質などに何か違いはありますか。
活動を始めた当時の子どもさんと今の子どもさんで、活動しているときの様子や性格・気質などに何か違いはありますか。 発足当初(15年前)は、まだ遊びの中で自然に触れあう子どもが多かったと思います。今の子はほぼその体験がありません。今の親世代が自然の中での遊びをあまり体験していないのかもしれません。
発足当初(15年前)は、まだ遊びの中で自然に触れあう子どもが多かったと思います。今の子はほぼその体験がありません。今の親世代が自然の中での遊びをあまり体験していないのかもしれません。 今の子どもさんたちにもっと生きものや科学に興味を持ってもらうためには何が必要でしょうか。
今の子どもさんたちにもっと生きものや科学に興味を持ってもらうためには何が必要でしょうか。 自分自身が体験し、気づきとそれを共有する場が大事と思っています。環境教育の教材のプロジェクトワイルドやプロジェクトウエットのプログラムの活用は、いいと思います。また、身近に起こっている環境問題を体験できる企画も興味をもってもらえます。
自分自身が体験し、気づきとそれを共有する場が大事と思っています。環境教育の教材のプロジェクトワイルドやプロジェクトウエットのプログラムの活用は、いいと思います。また、身近に起こっている環境問題を体験できる企画も興味をもってもらえます。 クラブで長く活動している子どもさんは、特にどういう点が成長していると感じますか。
クラブで長く活動している子どもさんは、特にどういう点が成長していると感じますか。 グループワークの時にリーダーとして積極的に活動できるようになります。また、活動の最後に参加者は全員感想や気づきを発表するのですが、その時にいちばん成長を感じます。回数を重ねるごとに、気づいてほしいことを発見できるようになっていきます。
グループワークの時にリーダーとして積極的に活動できるようになります。また、活動の最後に参加者は全員感想や気づきを発表するのですが、その時にいちばん成長を感じます。回数を重ねるごとに、気づいてほしいことを発見できるようになっていきます。
「リアルヴォイス」では、以下のようなクラブやメンバーたちをとりあげて紹介していきます。
 インタビューを受けてもいいよ☆というクラブのみなさん、
インタビューを受けてもいいよ☆というクラブのみなさん、
ぜひ全国事務局までメールをお送りください!